
朝の支度中、「早くして!」と何度も言ってしまい、子供がふくれっ面になる──。
そんな毎日を繰り返し、「もっと穏やかに関われたら…」と思ったことはありませんか?
私も2児の父として、毎朝このループに悩まされてきました。
そんな時に出会ったのが、スペインで育成年代を長年指導してきた佐伯夕利子さんの著書『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』です。
世界レベルのサッカー選手を育ててきたノウハウが、驚くほど子育てにもフィットします。

この記事では、本書『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』のエッセンスをもとに、
- 【教えないスキル】が子育てで役立つ理由
- まず身につけたいマインドセット3つ
- 明日から使える声かけ術3選
を私の経験も交えながら紹介します。
この記事を読み終えた時には、子供が自ら考え動き出し、親子の時間がもっと笑顔であふれる方法がわかります。
今日から一緒に、教えない育て方を始めてみませんか?
『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』とは?
本書は、サッカー大国スペインの育成年代を長年指導してきた佐伯夕利子さんの経験をもとに、選手が自分で考え、判断し、行動する力を育むための方法がまとめられています。
1973年イラン生まれ、福岡育ち。1992年にスペインへ渡り、2003年男子3部リーグで女性初の監督就任。ビジャレアルCFで育成・女子部統括を歴任し、日本ではJリーグ理事やWEリーグ理事を務める。スペインサッカー協会ナショナルライセンスレベル3、UEFA Pro ライセンス保持。著書に『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』(小学館新書)。
『教えないスキル』の一貫した主張

著者・佐伯夕利子さんは本書の中で繰り返しこう述べています。
指導者は、選手の学びの機会を創出するファシリテーターに過ぎない
答えを与えるだけでは、相手は受け身になり、思考力や判断力が育ちにくいです。
「教える」は指導者が主語ですが、「学ぶ」は選手が主語。
主体的に考える経験を重ねることで、自分で判断し行動できる力が養われます。
例えば、サッカーの試合後に「もっと早く右にパスしろよ」と指示するのは、ティーチング型のアプローチです。
代わりに「どうすればチャンスを増やせたと思う?」と問いかけると、選手は自分なりの解決策を考え始めます。このとき指導者は、答えを与えるのではなく考えるきっかけを提供しているのです。
手取り足取り教えるのではなく、主体的に学べる環境を意識的に作ることが大切です。
このアプローチは、スポーツだけでなく子育てやビジネスの現場でも変わりません。
子育てで【教えないスキル】が重要な理由

子育てにおいても、【教えないスキル】はとても重要です。
そもそも「教える」という行為は、裏を返せば「子供を自分の思い通りにコントロールしようとしている」状態とも言えます。
もちろん悪気はなくても、これが積み重なると、親も子供も疲れてしまいます。
人がイライラするのは、自分が描く「理想」と、目の前で起こる「現実」にギャップが生まれたとき。
子どもが理想通りに動かない瞬間、そのギャップがストレスになるのです。
- 「思い通りに動かそう」とする意識が減る
- 子供が自分で考える時間を持てる
- 親子の間に余裕と対話が生まれる
朝の準備で「早くしなさい」と繰り返す代わりに、
「今日は何からやる?」
と聞くと、子供は自分で順番を決めて動き始めます。
結果、親は命令する必要がなくなり、衝突も減ります。
【教えないスキル】は、イライラを減らしながら、子供が“自分で考えて動く力”を育てられる、一石二鳥の方法なのです。
まずインストールすべきマインドセット3つ
声かけ術だけを実践しても、子供はすぐに変わるわけではありません。
大事なのは、その前提となる考え方=マインドセットを親が持つことです。
ここでは、まず身につけたい3つのマインドセットを紹介します。
① 子どもの特性を理解
子供は大人と同じスピードや集中力で動けません。3〜6歳の注意持続時間は平均10〜15分とも言われます。期待値を大人基準にしてしまうと、イライラが増えるだけです。発達段階や性格を理解し、それに合わせた関わり方を意識しましょう。
② 親と子供の関係性
何を言ってもダメ出しされる環境では、人は心のシャッターを下ろし、意見をしなくなります。サッカーの現場でも、自由に意見を言えるチームほど選手は成長します。子育ても同じで、何を言っても受け入れてもらえる安心・安全な関係性があってこそ、子供は伸び伸びと行動できます。
③ 子育ての究極の目標
子育てのゴールは、親がいなくても自走できるようになることです。親の役割は「失敗させない」ことではなく、失敗してもそれを糧に前を向ける力を育てること。安全な環境の中で、失敗を経験させることこそが将来の大きな力になります。
明日からできる!育児でイライラしない声かけ術3選
ここまで紹介した3つのマインドセットは、いわば土台づくりです。
この土台があるからこそ、日々の声かけが子供に届き、効果を発揮します。
逆に、マインドセットがないままテクニックだけを真似しても、「一時的に言い方が変わっただけ」で終わり、子供の行動や考え方は根本的に変わりません。
では、この土台を踏まえたうえで、今日から実践できる「育児でイライラしない声かけ術」を3つ紹介します。サッカーの現場でも効果があった方法ばかりなので、ぜひ試してみてください。
オープンクエスチョンを投げかけよう

問いかけのルールとして、YESかNOで済ますことのできる質問(=クローズドクエスチョン)は避け、「どうして?」「どのように?」といったオープンクエスチョンを心がけましょう。
その理由は、YESかNOのクローズドクエスチョンは質問者(=親)が正解をすでに用意しており、質問者が回答権を握っている(=回答者に主導権)からです。一方で、答えが一つに決まらないオープンクエスチョン質問は、子供の思考を深めます。
ご飯をなかなか食べないときに
「早く食べなさい(命令)」や「ご飯食べない子は大きくなれる?(クローズドクエスチョン)」
と言うのではなく、
「どうすれば食べられるかな?(オープンクエスチョン)」
と聞くと、自分なりの解決策を考え始めます。
(うちの息子はこのやりとりで「デザートと一緒に食べる!」といって、渋々承諾しております。。。)
こうした問いかけは、子供に主導権を渡し、イライラをぶつける代わりに対話を生むきっかけになります。
無意味な「イイネ!」はやめよう!

(お!ここは褒めるタイミングだ!)と思う瞬間、ありますよね。
しかし、そのときにただ「いいね」と言うだけでは、子供には何が良かったのかが伝わりません。
行動心理学の研究でも、褒めるときは具体的な行動や成果を指摘するほうが、望ましい行動の定着率が高まるとされています。
さらに一歩踏み込んで「すごいね!なぜそう思って、その行動をとったの?」とオープンクエスチョンを加えると、思考やプロセスにも光が当たり、子供の発想を広げるきっかけにもなります。
ブロックで塔を作ったときに、
ただ「すごい!」と言うのではなく、
「高く積み上げられてすごいね!」(具体的に褒める)
「どうしてこの形にしたの?」(オープンクエスチョンを加える)
と伝えると、子供は自分の考えを言葉にし、他のアイデアを生み出す力も育ちます。
このように、褒める場面では「具体性+オープンクエスチョン」を意識することで、褒め言葉が単なる評価ではなく、学びのきっかけになります。
サンドイッチ話法を使おう

サンドイッチ話法は、「良い点 → 改善点(=本題) → 励まし」の順で伝える方法です。
注意や改善点を伝えるときでも、相手の気持ちを守りながら前向きに受け止めてもらえます。
本題に入る前に相手を褒め、改善点を伝え、最後に期待や応援の言葉で締めくくることで、「叱られた」「ダメ出しされた」という印象を避けられます。
「お、今日はおもちゃの片付け早かったね(良い点)」
↓↓
「明日は本もきれいにそろえてみよう(改善点)」
↓↓
「そしたらもっと気持ちいいね!(励まし)」
私自身、中学校のサッカー部で監督から
「お前は技術もあって、〇〇もできて素晴らしい(褒め)」
「でも、感情的になるところが非常にもったいない(改善点)」
「頭は良いんだから次の試合から変わってくれよ(励まし)」
と言われたことがあります。
一言一句は覚えていませんが、温かい気持ちと「期待されている」という感覚は鮮明に残っています。
人は何を言われたかではなく、どんな気持ちにさせられたかを覚えている生き物ですと述べています。
サンドイッチ話法は、子供との関係を守りながら改善を促すための有効な方法です。
ぜひ今日から意識してみてましょう。
実践するためのポイント
① 一つできればOKと考える
最初から全部やろうとすると、必ず挫折します。
まずは「これならできそう」と思える方法を1つだけ選び、生活に取り入れてみましょう。
- 例:「朝の準備の声かけだけオープンクエスチョンにする」
- 例:「褒めるときに具体性を加える」
小さな成功体験が自信につながり、自然と他の方法も取り入れやすくなります。
② パートナーと協力する
夫婦やパートナー間で育児方針や声かけ方法を共有することはとても重要です。
どちらか片方だけが意識しても、子供は混乱してしまいます。
- 例:「褒めるときは具体的に」「命令ではなく問いかけ」などルール化
- 育児日記やチャットで共有すると、ぶれにくい
同じ方向を向いて子供に関わることで、家庭全体の一貫性が生まれます。
③ 【できればやりたい】親の言動を記録する
自分がどんな声かけをしているかは、意外と客観的に把握できないものです。
佐伯さん自身も、現場での指導中にピンマイクで自分の声を録音して振り返ったそうです。
- 朝の忙しい時間帯だけでも、スマホの定点カメラや録音アプリで記録
- 後で聞き返すと、「思った以上に命令が多い」「褒め言葉が少ない」など新しい気づきが得られる
最初は少し勇気がいりますが、改善のきっかけになる貴重なフィードバックになります。
まとめ:教えないスキルは、親子の未来を変える
佐伯夕利子さんが提唱する【教えないスキル】は、サッカーの育成現場だけでなく、私たちの日常の子育てにもそのまま応用できます。
これらはすべて、子供が自分で考え、判断し、行動する力を育むための土台です。
もちろん、親も人間ですから、毎回完璧にはできません。
でも、1日1回のオープンクエスチョンや、具体的な褒め言葉から始めるだけで、親子の空気は少しずつ変わっていきます。
将来、子供が自分の足で人生を歩き出すその日まで――。
今日の小さな声かけが、きっとその力強い一歩を支えるはずです。
だから、まずは「一つできればOK」の気持ちで、試してみませんか?
あなたの家庭にも、もっと余裕と笑顔が増えていくはずです。
『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』では、今回ご紹介した内容をはじめ、佐伯さんが現場で培った具体的な声かけ例や失敗談、組織づくりのヒントまで詳しく解説されています。
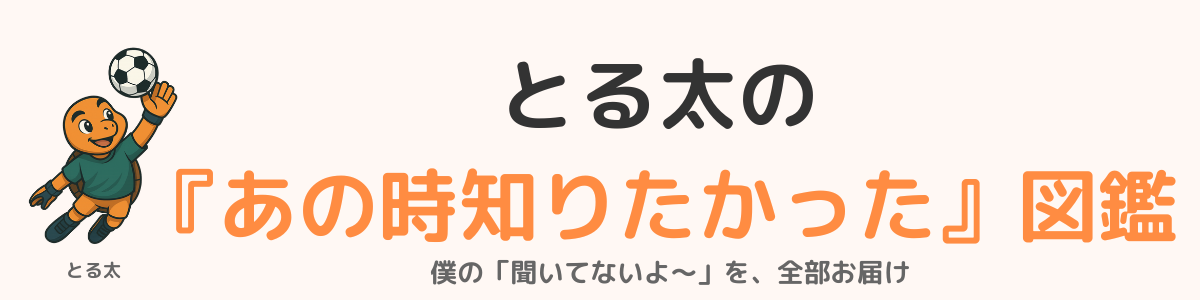

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b4bb6a1.02625792.4b4bb6a2.6df6d83b/?me_id=1213310&item_id=20234371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3913%2F9784098253913_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





コメント