
僕自身もコーチを始めた頃、団子サッカーに頭を抱えていました。
声を張り上げてもなかなか変わらない…。
でも勉強と実践を繰り返して改善していけると気づきました。
今は保護者に説明できる自信もつきましたよ。
団子サッカーは小学生低学年では自然に起きる現象です。しかし適切なアプローチをとることで、改善のスピードを早めることができます。
本記事では、現場で効果を実感した 明日からできる団子サッカー解消法3選 を紹介し、実践時の注意点まで解説します。
記事を読み終える頃には「なるほど、だから団子になるのか!」と納得し、今週末の練習からすぐ試せる具体的な方法が手に入ります。さらに、保護者に「こういう段階だから心配しなくて大丈夫」と説明できるようになり、チーム全体で子どもたちの成長を応援できるはずです。
『団子サッカー』とは?
小学生低学年の試合でよく見られる『団子サッカー』。
実はこれ、ただの“あるある”現象ではなく、子どもの成長段階や指導方法と深く関係しています。
ここではまず、団子サッカーの意味と、とる太が考える向き合い方を整理していきます。
そもそも『団子サッカー』って何?

低学年の試合で、子どもたちがボールの周りに密集して動く様子を指します。
まるで団子のように一つの塊になり、ボールの近くに全員が集まってしまう状態です。
とる太の『団子サッカー』に対する考え方

『団子サッカー』そのものは自然な現象です。
年齢や経験が浅い小学生低学年までの時期には、誰もが通る道です。
ただし、「自然だから放っておく」で終わらせると、学びのきっかけを逃してしまいます。
新入社員も最初の仕事っぷりはぎこちないですよね?
そこで「まぁ最初は仕方ない」と思いつつ、上司や先輩が適切に声をかけたり環境を整えたりするのと同じです。
団子サッカーもコーチのアプローチ次第で大きく変わります。これからその方法を見ていきましょう。

とる太コーチの見解は、
“団子サッカーは自然な現象ではあるけれど、コーチがどうアプローチするかが大切”
となります
『団子サッカー』が起こる主な原因3つ
具体的な解決策に入る前に「なぜ団子サッカーが起きてしまうのか」を理解しましょう。
原因はさまざまで、網羅することは難しいですが、この記事では大きく3つを挙げます。
子どもの年齢特性

低学年の子どもは「ボールと自分」だけに意識が向く発達段階にあります。
つまり、「ボールそのものが目的」であり、ポジションや味方との距離は考えることが難しいのです。
ピアジェの発達理論においても、7歳前後の児童には以下の特徴があるとされています。
- 自己中心的思考が強く、他者の気持ちや立場を理解するのが難しい
- 複数の事柄を同時に考えるのが難しく、1つのことに集中しがち
一方で、9、10歳になるにつれ、「脱自己中心化」が進み、他者視点や協調性、共感性が少しずつ育まれるとされています。
サッカーに置き換えると、U6では「目の前のボールを追う」ことが最優先ですが、U8になると徐々に空間認知が広がり、U10では味方との距離感やパスの選択肢が見えてきます。
これはイングランドのFAコーチングライセンス講習でも発達段階の特徴として説明されていました。
こうした年齢特性があるため、低学年では団子状態になりやすいのです。
年齢別にイングランドのFAコーチングライセンス講習で学んだ当時のメモを今後まとめたいと思います!
参考までにJFAが提示しているものは以下の通りです。
▶U6年代…【自分とボール】 はじめのうちは自分とボールだけの関係です。とにかくボールは自分のものとして追いかけ続けます。
▶U8年代…【自分と相手とボール】 次に自分をじゃまする相手という存在が現れます。自分のボールを取りに来るのはみな相手。相手も味方もわかりません。
▶U10年代…【自分と味方みんなでプレー】 それからチームとして、味方となるグループと相手となるグループがわかりはじめます。
▶U12年代…【チームの中の自分 チーム対チーム】 チームでチームを相手にするということがわかってくると、チームの中の存在としての自分が理解できるようになります。
日本サッカー協会『JFAキッズ U8/U10 ハンドブックより』
https://www.jfa.jp/youth_development/players_first/pdf/u8u10.pdf
サッカーを観ない、知らない

日本においてはまだ「サッカーを観る文化」が少ないと感じます。
サッカーをあまり観ていない子は、試合の流れやポジションの役割を理解できません。
一方で、ヨーロッパの子どもたちは、日常的にテレビやスタジアムでサッカーを目にするため「ポジションを取るんだ」「パスを使って攻めるんだ」といった動きを自然にイメージできます。
日本でも野球の文化はあるので、「打ったら一塁側に走る」ことは誰でも理解しているのと同じことです。(欧州の子どもに野球をさせたら三塁側に走り出すかもしれませんね笑)
実際、私が指導している少年サッカーチームでも、子どもたちに「昨日の日本代表/チャンピオンズリーグ決勝の試合を見た?」と聞くと半分くらいが「ない」と答えるのが日常です。
「見た!」と毎回答える子はポジショニングの理解が早いと感じています。
だからこそ、家庭で一緒にサッカーを観るだけでも大きな効果があります。チームの成長を加速させる第一歩は、まず観ることから始まります。
コーチの工夫がない

コーチの意図や工夫がないまま、小学校低学年に6年生と同じ8人制を行えば、団子になるのは当然です。
挙げればキリがないですが、低学年で8人制を行うと以下のような現象が頻発します。
- 人数:8人は多すぎで、複数の味方・相手を同時に認識できない
- コートサイズ:広すぎて、ゴール前まで運べず、一度自陣に押し込まれると抜け出せない
- ゴール:大きすぎて、GKがほとんど止められない
- オフサイド:他者を認識できないのでルールが理解できない
- ゴールキック:キック力がないので全部ピンチ
私がイングランドで研修を受けたとき、現地のコーチが「日本の低学年が8人制をやっている」と聞いて本気で驚いていました。発達段階を無視したルールでは、子どもが本来得られる学びを逸します。
だからこそ、まずは人数・コートサイズ・ルールを子どもに合わせて変えること。これだけでも自然と動きが変わり、団子サッカーからの脱却が始まります。
明日からできる団子サッカー解消法3選
団子サッカーは「自然に起こるもの」ですが、練習の工夫次第で少しずつ改善できます。
ここでは私が実際に指導の現場で使い、効果を実感した3つの方法を紹介します。
すぐに取り入れられる内容なので、今週末の練習からでも実践可能です!
フニーニョ

フニーニョは、英語の“Fun”(楽しさ)とスペイン語の“Niño”(子ども)を組み合わせた造語です。ドイツ人のホルスト・ヴァイン氏によって考案されました。
細かいローカルルールは国や地域によって違いますが、大雑把に言うと「3vs3の4ゴールゲーム」といえば理解しやすいでしょう
- 人数は3vs3
- 各チームにミニゴール2つずつ設置
- GKはなし
- 出たらドリブルインかキックイン
- シュートゾーン超えてからでないとシュートできないシュート
- オフサイドなし
- 3vs3の少人数なのでボールタッチ数が増える(従来の7人制より約60%増加)
- ゴールが両サイドにあるので、自然と広がりやすく、「スペース」の概念を学べる
- GKなしかつ複数のゴールで、得点が入りやすく、成功体験や自信が得られやすい
- ゴールは何個ある?どっちのゴールが空いてる?
- パスができなかったらどうする?
- どこに走ったら点取れそう?
低学年のうちは毎日このゲームで1日を締め括るのもアリだと思います。
ドイツではこのルールが低学年年代の公式戦になっているそうです。
日本サッカー協会も各チームに委ねるのではなく、この試合形式を公式戦ルールにしてもらえるとより普及すると思うのですが・・・
2vs1ロンド

ロンド(Rondo)は、ヨーロッパの育成現場では欠かせない「ボール回し」のトレーニングです。
日本でも「鳥かご」と呼ばれ、高学年では「3vs1」「4vs2」はよくみかけますね。
2vs1から始めると低学年でも理解しやすく、サッカーの基本的な要素がたくさん詰まっています。
- 2人の味方と1人の鬼を1つのピッチに全組入れる
- パスを通したら1点(1番点を繋げたペアが勝ち)
- 鬼は以下3つの方法で交代
①鬼がボールを足でカットしてから手でキャッチ
②ボールがコートの外に出る
③他のグループと人やボールがぶつかる - 【アレンジ】ワンツーが決まったら近くのゴールにシュート
- 「ボールと自分」以外に「仲間」と「相手」を意識することができる
- 「今パスを出すべきか、ドリブルで引きつけるべきか」判断する力が育つ
- パスをもらうための工夫が身に付く(広がる、パスをしたら走る、サポートするなど)
- どのくらいの距離にいるとパスしやすい?
- パスした後、どうすれば仲間を助けられる?
- 仲間はどこにいる?相手は取りにきてる?
2vs1ロンドは非常にシンプルですが、低学年が「広がるとパスしやすいんだ」と気づくのに最適です。
繰り返し行うことで、試合でも自然と距離感を覚え、団子状態から少しずつ抜け出していけます。
ウォーミングアップは全部コレでもいいかもしれませんね!
ボール欲しい人〜?

最後はメニューというより、普段の練習にすぐ取り入れられる“工夫”です。
リスタートやボール出しの場面で、ただ近い子に渡すのではなく「積極的に呼び、なおかつ広がっている子」にボールを入れるだけで雰囲気が変わります。
- 練習や試合形式でボールを出すとき、コーチは必ず「広がって呼んでいる子」にボールを渡す
- 声を出していない、密集している子にはあえて出さない
- 「広がると得をする」という経験が積み重なり、自然とポジションを取る意識が高まる
- 声を出して自己主張する習慣がつき、試合中のコミュニケーションにもつながる
- パスをもらえる人・もらえない人の違いを実感できる
- 「ボール欲しい人〜?」
- 「一番いい場所にいるのは誰かな?」
「広がって呼べばコーチからボールがもらえる」という共通認識があるだけで、子どもの意識は大きく変わります。練習のどんなメニューにも応用できるので、明日から気軽に取り入れてみてください!
注意点
ここまで3つの解消法を紹介しましたが、大切なのは「やり方を間違えないこと」です。
実践そのものはシンプルでも、声かけや環境づくりを誤ると逆効果になりかねません。
ここでは特に押さえておきたい3つの注意点を紹介します。
時間がかかることを理解する

団子サッカーは一朝一夕で直るものではありません。
発達段階の影響が大きく、どれだけ工夫しても「少しずつ改善する」のが自然です。
会社の新人育成でも子育てでも、「実践したら即改善する」ことばかりではないですよね。
「すぐに結果が出ない」と焦る必要はありません。
毎回の練習で小さな成長を見逃さず、認めてあげることが、子どものモチベーションや成長に繋がります。
「広がれ」と指示・命令しない

子どもは「広がる理由」を理解しないまま命令されても、次の瞬間にはまた団子に戻ります。
重要なのは行動の意味を体験で気づかせることです。
ここで役立つのが佐伯さんが提唱する【教えないスキル】!
「広がれ!」ではなく「ボールをもらいやすいのはどこかな?」とオープンクエスチョンを駆使して問いかければ、子ども自身が考えて動くようになります。
保護者を巻き込む

子どもにとってコーチ以上に影響力があるのが保護者です。
練習や試合を見て「なんで団子になってるの?」と不安に思う親御さんも多いでしょう。
だからこそ「今はこういう段階です」「チームとしてこういう工夫をしています」「家ではこういう問いかけをしてください」と説明することが大切です。
(資料や保護者会を適宜設けて共有することを勧めます!)
保護者が納得すれば、子どもへの過度な指示や教え込みも減り、家庭とチームが同じ方向を向けます。
まとめ
団子サッカーは「低学年あるある」ですが、決して放置していいわけではありません。
子どもの年齢特性を理解し、コーチが工夫を加えることで少しずつ改善していきます。
今回紹介した3つの方法(①フニーニョ ②2vs1ロンド ③ボール欲しい人)は、どれもシンプルで今すぐに実践できるものです。大切なのは「命令」ではなく「問いかけ」て「気づかせる」こと。
そして保護者も巻き込みながら、長い目で成長を見守ることです。
短期間で完璧に変わることはありませんが、子どもたちの小さな変化を積み重ねていくうちに、気づけば団子状態から抜け出し、自然と広がるサッカーができるようになります。
団子サッカーは“伸びしろのサイン”です。コーチや保護者の工夫次第で、子どもたちのプレーも楽しさも大きく変わります。ぜひ、次の練習から試してみてください。
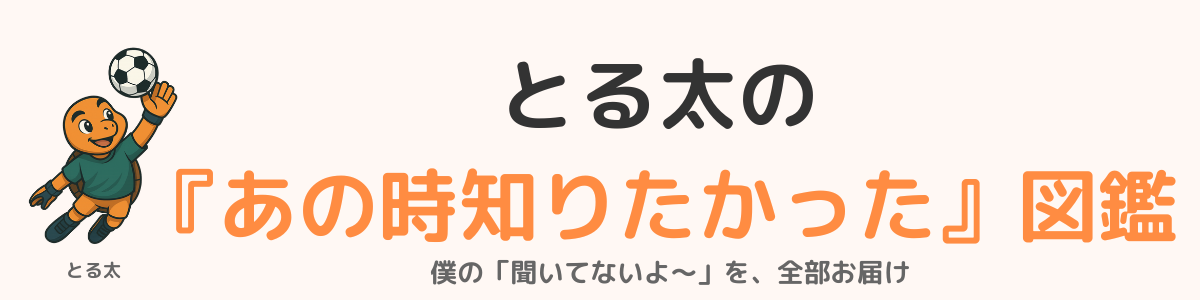




コメント